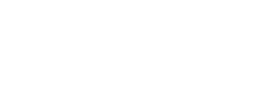七五三の縁起物「千歳飴」、なぜ千歳飴というの?
七五三HOW TOお子さんの成長に感謝し、これからの長寿と健康を願う七五三。最近では、神社やお寺にお参りしたり、家族で食事を楽しんだり、記念写真を撮ったりしてお祝いするご家庭も増えています。
そんな七五三のお祝いの中で、神社やお寺でのご祈祷の際にもらえることがある「千歳飴(ちとせあめ)」。七五三といえばこの飴を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか?実は、この千歳飴には、しっかりとした意味が込められているのです。
この記事では、七五三に欠かせない千歳飴の由来や意味について、わかりやすくご紹介します。

七五三の祝菓子「千歳飴」

「千歳飴」の意味は?
千歳飴(ちとせあめ)」の“千歳”には、<長い年月>や<千年>という意味があります。その名の通り、千歳飴は“長さ1メートル以内・直径1.5センチ以内”と形が決まっており、細長いのが特徴です。
この長い形や、飴を引っ張って伸ばす製法から、「細く長く」「長寿」というイメージが重ねられ、「長く粘り強く、いつまでも健康でいてほしい」という願いが込められています。
もともとは縁起の良い“紅白の飴”がセットになったものが主流でしたが、最近では、かわいいパッケージやいろいろなフレーバーの千歳飴も登場しており、より身近に楽しめるようになっています。
「千歳飴」の始まり
千歳飴の始まりにはいくつかの説があります。ここでは、広く知られている2つの由来をご紹介します。
まず1つ目は、大阪発祥とされる「千歳飴(せんざいあめ)」の説です。大阪で商売をしていた平野甚右衛門という人物が、のちに江戸へ移り、浅草の浅草寺の境内で紅白の棒状の飴を売り始めたのが始まりとされています。当時は同じ漢字で「せんざいあめ」と読まれていましたが、のちに「ちとせあめ」と呼ばれるようになったと伝えられています。
もう1つは、江戸の飴売りが紅白の棒状の飴を「千年飴」と名づけて売り出したという説です。紅白の見た目と「千年」という名前が縁起が良いと評判になり、長寿を願う縁起物として広まったと言われています。また、この飴は鶴や亀、松竹梅といった縁起物が描かれた細長い袋に入れて販売されたとも伝えられています。
千歳飴の正しい食べ方とは?
「長寿を願う千歳飴、せっかくなら丁寧に食べたい。でも、長くてそのままでは食べにくい…」
そんな時、「切ってもいいの?」「縁起が悪くならない?」と不安になるママやパパもいらっしゃるかもしれません。
でも、ご安心ください。千歳飴には決まった食べ方はなく、無理に一気に食べる必要もありません。地域によって考え方に違いはありますが、食べやすいように切ったり砕いたりしてOKなんです。
実は、飴を折って分けることを「福を分ける」と捉える考え方もあり、マナー違反にはなりません。
お子さんに合わせて、安全に食べやすいサイズにしてあげましょう。
もし「硬くて食べにくい」と感じたら、電子レンジで少し温めると柔らかくなり、食べやすくなります。
また、飴として食べきれなかった場合は、コーヒーや紅茶に入れて砂糖代わりにしたり、他のおやつにアレンジして楽しむのもおすすめ。やさしい甘さが広がりますよ。せっかくの縁起物。家族みんなで、楽しく美味しく千歳飴を味わってみてはいかがでしょうか?
「千歳飴」はどこで手に入る?

七五三のとき、着物姿のお子さんが手にしている印象が強い「千歳飴」。
「でも、実際にはどうやって手に入れているの?」と疑問に思うママやパパもいらっしゃるのではないでしょうか?
ここでは、千歳飴の主な入手方法をご紹介します。
・神社やお寺でのご祈祷の際に
ご家族で神社やお寺にお参りしてご祈祷を受ける場合、授与品として千歳飴をいただけることが多いです。他にも、お守りや記念品が一緒に渡されることもあります。
ただし、すべての神社やお寺で用意されているとは限らないため、確実に欲しい場合は、事前に参拝予定の場所へ問い合わせてみるのがおすすめです。
・ スーパーやデパート、和菓子屋さんで
七五三シーズンになると、スーパーやデパート、お菓子屋さんの店頭にも千歳飴が並ぶようになります。
神社などで授与されるものとは違ってご祈願はされていませんが、気軽に購入でき、価格も比較的リーズナブルです。
お店によっては、味やデザインが豊富にそろっていることもあり、選ぶのが楽しくなりますよ。
・ オンラインショップで購入する
インターネット通販でも、千歳飴は簡単に手に入ります。
時期を問わず注文できるので、昔ながらの定番から、おしゃれで個性的なデザインのものまで幅広く選べます。
ただし、配送に日数がかかる場合があるため、必要な日を逆算して早めに注文するのがポイント。
特に七五三シーズンは混み合うこともあるので、余裕を持って準備しておくと安心です。
千歳飴の袋、絵柄にも大切な意味があります

・鶴亀
「鶴は千年、亀は万年」と言われるほど、鶴・亀は長寿を象徴する吉祥の動物として尊ばれてきました。
鶴は、寿命が長く鳴き声が遠くまで、響くことから「天にいる神様にまで、声が届く、めでたい鳥」と考えられています。
亀は、中国で古来より、仙人のいる不老長寿の池・蓬莱山の使いと言われていて、また甲羅の六角形模様は吉兆を表す図形としても有名です。
・松竹梅
1年中緑を保つ松は、樹齢も長く何十年から何百年と長く、長寿の象徴とされています。
竹は、まっすぐに伸び、地面に根をはって新芽を出すことから、子孫繁栄の象徴です。梅は寒い冬でも豊な香りを放って花を咲かせることから、生命力や気高さを表すものとされています。
冬の寒い時期で枯れることなく、緑や花が楽しめる松竹梅は、生命力の強い神秘的な植物として尊ばれてきました。
・高砂の尉と姥
伝統的な千歳飴の袋には、見慣れないおじいさんとおばあさんが描かれた袋もあります。熊手をもつおじいさん『尉(じょう)』と、箒をもったおばあさん『姥(うば)』は高砂神社の松に宿る神様を具現化した図柄で、厄を掃き、松の葉をかき集める姿が、夫婦円満や長寿の象徴として描かれています。七五三だけでなく様々なお祝いの場において広く用いられている図柄です。
まとめ

いかがでしたか?
七五三は、子どもの健やかな成長を願い、厄除けの意味を持つ大切な行事です。そして、「千歳飴」の“千歳”という言葉には、「千年生きるほど、元気で長生きしてほしい」という親の深い願いが込められています。
長寿を願って食べられてきたこのお祝いの飴。ぜひ、お子さんと一緒に、千歳飴に込められた想いや七五三の意味を話しながら、素敵な時間を過ごしてみてください。心に残るあたたかなお祝いになりますように♪